はじめに
発生学、幹細胞学、組織工学技術など様々な研究分野の数々の進歩により、再生医療は容易になりました。 再生医療の第一世代は、組織由来の幹細胞、胚性幹(ES)細胞、人工多能性幹(iPS)細胞などを用いた幹細胞移植療法である。 例えば、白血病や低形成性貧血の治療には、すでに骨髄移植が一般的になっています。 また、白血病、パーキンソン病やアルツハイマー病、心筋梗塞、糖尿病、肝疾患など、多くの病気やケガに対して、ES細胞やiPS細胞の臨床試験が始まっている。 組織再生は再生医療の第二世代と位置づけられ、皮膚や軟骨などいくつかの製品がすでに市場に出ている。 さらに、加齢黄斑変性症を治すために、患者または匿名ドナー由来のiPS細胞を用いた世界初の組織再生治療が臨床試験で検討されています。 この10年間で、幹細胞生物学と発生生物学の分野の進歩は、機能的な臓器を再生する新しい機会を提供しました。 胚発生の過程で、臓器は、個々の臓器形成分野に応じて、運命的に決定された上皮性幹細胞と間葉性幹細胞の相互作用によって誘導されるそれぞれの臓器原基から発生する(図1a) 。 2007年、胚性器胚から分離した上皮性幹細胞と間葉性幹細胞を用いて、器官誘導能を有するバイオエンジニアリング器官胚を作製する新しい細胞操作法を開発し、機能的器官再生を初めて実現しました(図1b)。 この先駆的な研究とその後の研究により、複数の種類の外胚葉性器官が完全に機能的に再生されることが報告され、機能的器官再生の概念を裏付ける証拠となりました。 胚の器官形成と器官再生のアプローチを模式的に示す。 (a)器官形成の模式図。 器官形成野の確立、上皮と間葉の相互作用による器官原基の形成、形態形成を経て、機能的な器官が形成される。 (b) 器官誘導能を有する胚性運命決定上皮・間葉系幹細胞を用いて器官原基形成を模倣し、外胚葉性器官を完全に機能的に再生させるスキーム。 (c)多能性幹細胞から発生した細胞塊に器官形成野を形成させることを再現したオルガノイド発生の模式図
次のパラダイムシフトは、2008年にES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞や組織幹細胞から生じた細胞塊に器官形成野を誘発させて生成するオルガノイドの発見である(図1c)。 大脳皮質、下垂体、視蓋、内耳などの中枢神経系を含む、ほぼすべての種類のオルガノイドを作製することができる(図1c)。 オルガノイドの出現は、基礎生物学や臨床応用に不可欠な技術的ブレークスルーであるが、オルガノイドはまだ元の臓器の構造や機能を部分的にしか再現できていない。 したがって、これまでに作製された単一のオルガノイドの大半は、完全な臓器の限られた、あるいは部分的な機能を代替することができ、したがって、現在ではミニ臓器と見なされている。 最近、唾液腺オルガノイドの開発に成功し、同所移植により完全に機能する臓器再生が実証されました。 外胚葉性臓器の発生原理は他の臓器と類似しているため、他の臓器を完全に機能的に再生するためには、外胚葉性臓器の再生について深く理解することが重要である(図1a)。 さらに、in vivoオルガノイド法を用いた外皮臓器系(IOS)の再生は、臓器系再生の可能性を明確に示した。
このレビューでは、発生生物学と幹細胞生物学をベースに、様々な幹細胞集団と戦略を用いた臓器再生に関する最近の進展を述べ、次世代の臓器再生医療としての臓器置換療法の将来の方向性について議論する。
胚細胞を用いた三次元細胞操作法「器官胚芽法」の開発
研究者は数十年にわたって、機能細胞、足場材料、生理活性物質を組み合わせて組織工学的手法で臓器を再生することを試みてきた. これらの先行研究は、臓器再生に向けて一定の貢献をしたものの、臓器誘導の効率が低いこと、再生された臓器の方向や大きさが制御できないことなど、これらの研究から得られた知見に関してかなりの懸念が存在している。 幹細胞や発生生物学の進歩に伴い、胎児期における器官形成の再現は過去30年の間に進歩している。 器官再生の発生過程は、初期発生におけるボディプランの確立後に形成される器官野の上皮間葉相互作用による器官原基の誘導から始まる。 器官原基の再生を目指した細胞操作技術が長年開発されてきたが、機能的な器官の発生・再生を完全に再現することはできなかった。
我々は、発生初期の上皮・間葉相互作用による器官原基の誘導を再現する生物工学的手法(器官原基法)を開発した。 マウス胚から分離した上皮細胞と間葉系細胞をI型コラーゲンゲルの中に高密度に区画化し、器官形成の過程を精密に再現することを試みた。 この新しい方法を用いて、歯、毛包、分泌腺など、複数の種類の外胚葉性器官の機能的再生を観察した。
完全機能的バイオエンジニアリング歯
3.1. 歯の発生
歯胚の発生では、まず歯質のラミナが厚くなる(ラミナ期)(図2a)。 歯胚は口腔粘膜上皮や間充織と相互作用しながら発達する。 その後、マウスの胚11-13日目に上皮シグナルにより、将来の歯の位置での上皮の肥厚と、その下の神経堤由来の間充織への上皮の出芽(bud stage)が誘導される。 EDs13-15では、エナメル質の結び目が歯乳頭の形成と維持を担うシグナルセンターとして機能する。 一次エナメルノットは歯芽で形成され、歯芽から歯冠期への移行期に出現する。 ED17-19では、歯胚の上皮細胞と間葉系細胞が終末分化する 。 間葉系細胞は歯髄や歯周組織にも分化し、セメント質、歯根膜、歯槽骨となる。 歯冠形成後、歯根形成が開始され、成熟した歯が口腔内に萌出する。
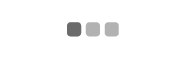
図2. バイオエンジニアリングによる完全機能的な歯の再生。 (a)歯の発生スキーム。 (b)移植したバイオエンジニアリング歯胚(i)とGFP導入マウス由来細胞による再生歯(ii)の萌出時間経過の解析。 スケールバー。 500 µm。 (c) 再生歯牙の組織学的解析。 バイオエンジニアリングされた歯は、エナメル質、象牙質、歯髄、歯周組織からなる正しい歯質も形成していることがわかる。 スケールバー:200μm
3.2. 完全機能的な歯の再生
う蝕、歯周病、外傷による歯の喪失は、適切な口腔機能の根本的な問題を引き起こし、口腔および全身の健康問題に関連します。 歯を失った後の咬合機能の回復を目的とした従来の歯科治療は、固定式または可撤式の義歯やブリッジなどの人工材料で歯を補うことが基本となっています。 これらの人工的な治療法は歯科疾患の治療に広く応用されているが、歯は周囲の筋肉の咬合力や矯正力と協調し、生後の顎の成長期に咬合システムを確立することで顎口腔系の完全性が保持されるので、咬合の回復が必要である … 最近の組織再生の進歩により、骨のリモデリングによる歯の下層の発育促進や、有害な刺激を感知する能力の補助など、生体歯の機能を高めることが可能になりました。
我々の以前の研究で示したように、生体工学的歯胚は、失った歯の領域に移植すると正しい歯構造に成長し、口腔内に正常に萌出する(図2b)。 また、成熟歯からなるバイオエンジニアリング成熟歯ユニットを移植した場合、レシピエントの骨統合により歯周靭帯や歯槽骨を歯の喪失部位に生着させることができる(図2c)。 バイオエンジニアリング歯は、骨との一体化に成功することで、バイオエンジニアリング歯ユニットに由来する歯根膜や歯槽骨との相互作用を維持することができます。 バイオエンジニアリング歯のエナメル質と象牙質の硬度は、ヌープ硬度試験で分析したところ、正常範囲内であった。 将来の方向性として、歯の形状の制御が重要であると考えられている。 歯は、発生過程で間充織をボディプランに沿うように誘導することで生成される。 歯の形態制御に関しては、歯の幅は上皮細胞層と間葉細胞層の接触面積で制御され、歯頸部の数はエナメル質内上皮のShhの発現で制御される 。 このバイオエンジニアリング歯技術は、次世代治療法として歯全体を置換する再生治療の実現に貢献します。
完全機能化バイオエンジニアリング毛包
4.1. 毛包の発生
マウスには背中に4種類の毛があり、ガード毛、アウル毛、オーセン毛、ジグザグ毛に分類されている。 マウスの背部皮膚における毛包の発生は、ED10.5頃に間葉系細胞の運命決定から始まり、真皮コンデンセートが形成される。 真皮凝縮体とその上にある表皮との相互作用により、毛包が誘導されます(図3a)。 毛包が形成されると、3つの波が生じ、ED14.5のガードヘアから始まり、ED17のオーシャンヘアー、そして出生時のジグザグヘアーへと続いていく。 毛包上皮の下端は、凝縮した真皮細胞に巻きついて、毛母細胞の胚を形成している。 凝縮真皮細胞は毛包間葉系幹細胞のニッチとされる真皮乳頭を形成し、毛母細胞の分化を誘導し、毛包の内根鞘や毛幹を形成する。 バルジ領域は上皮幹細胞ニッチも形成し、同時に神経線維や立毛筋とも結合している(図3a).
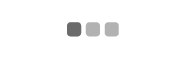
図3. 完全に機能的なバイオエンジニアリングによる毛包の再生。 (a)毛包の発生スキーム。 (b)バルジ上皮細胞(緑)と毛乳頭販売(赤)から生成された代表的なバイオエンジニアリング器官胚。 (c) バイオエンジニアリングされた毛髪のマクロ形態観察(矢頭)。 (d) アセチルコリン(ACh)投与による毛生え能力の解析。 白矢印はACh注入前、黒矢印はACh注入後。 スケールバー。
4.2. 毛包の完全な再生
毛という器官は、体温調節、紫外線からの物理的絶縁、防水、触覚、有害刺激からの保護、カモフラージュ、社会的コミュニケーションといった生物学的機能を有している。 先天性毛包形成不全や男性型脱毛症などの脱毛症は、心理的苦痛を与え、男女のQOLに悪影響を及ぼします。 現在の薬物療法は、先天性毛包形成不全や円形脱毛症などの脱毛症を理想的にコントロールするのに十分ではありません。 2134>
ヘアサイクルにおいて、毛包の原基は周期的に再構成され、毛包を再生する能力を持つ上皮性幹細胞や間葉性幹細胞が成人でも存在しています。 したがって、この臓器は成体由来の細胞から再構成原基を再生できる唯一の臓器である。 健康な頭皮部分から1個の毛包を分離し、男性型脱毛症患者に移植する自家毛包移植が報告されており、移植された毛包はその特性を維持しています。 多くの研究者によると、毛包の中の成熟した毛球から採取した間葉系細胞を用いて皮膚の真皮細胞を置き換えることで、新しい毛包の形成が誘導されるとのことです . しかし、周囲の組織と協調して機能する毛包の再生は困難である。 私たちのグループは、胚だけでなく成体マウスから分離したバルジ由来の上皮細胞や皮膚乳頭細胞を用いて、間葉系幹細胞を含むバイオエンジニアリング毛包胚を再構成した(図3b) 。 バイオエンジニアリングされた毛包原基は、同所移植後、適切な構造を持つ成熟した毛包に成長し、生涯にわたって毛髪を生成します(図3c)。 さらに、再生した毛包は周囲の宿主組織と効率的に結合し、アセチルコリン投与に反応して毛運動反射を示しました(図3d)。 本研究は、成体毛包から分離した組織幹細胞がヒト毛包に成長する可能性を示し、再生医療分野への応用が期待されます。
完全機能型バイオエンジニアリング分泌腺
5.1. 唾液腺・涙腺の発生
唾液腺や涙腺などの分泌腺は、口腔や眼球表面の微小環境における保護や生理機能の維持に不可欠である。 分泌腺は、上皮と間葉の相互作用によって発達する。 唾液腺は、耳下腺(PG)、顎下腺(SMG)、舌下腺(SLG)の3種類に大別される。 SMGは、ED11で上皮が間葉系領域に浸潤して発達する。 侵入した上皮組織は増殖し、上皮の茎を形成する(図4a)。 終芽は裂け目を発達させ、ED12.5-14.5からの伸長と分岐を繰り返すことにより、枝分かれした構造を形成する。 終末芽はアシナール細胞に分化し、ED15で秘書タンパク質を合成するように成熟する。 一方、涙腺もED12.5で上皮が眼球の側頭部にある間葉系嚢に侵入し、発達する。 丸みを帯びた上皮芽は上結膜前庭に凝縮し、周囲の間充織に侵入する。 涙腺胚は茎の伸長と裂孔形成の形態形成を介して枝を形成する。 涙腺の基本構造はED19 .
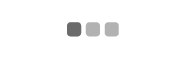
Figure 4.涙腺の基本構造は、ED19 .
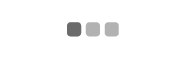
により達成される。 バイオエンジニアリングによる器官原基とオルガノイドからの完全機能的な唾液腺再生。 (a)唾液腺発生の模式図。 (b)バイオエンジニアリングされたSMGの移植の模式図。 バイオエンジニアリングされた胚芽は、PGの位置で管との接続を促進するために、ナイロン糸で移植された。 スケールバー:200 µm。 (c) 唾液腺欠損マウスにおける移植後 30 日目のバイオエンジニアリング SMG の写真。 (d) クエン酸による味覚刺激後の正常マウス(ライトバー)およびバイオエンジニアリングSMG移植マウス(ダークバー)の唾液分泌量の評価。 データは平均値±s.e.m.で示した。スケールバー:200 µm。 (e) 唾液腺欠損マウスに移植後30日目のマウスES細胞由来のGFP標識唾液腺の写真。 スケールバー:200μm。 (f)水(右バー)またはクエン酸(左バー)で刺激した後の複合唾液腺オルガノイド移植マウスにおける唾液の分泌量の評価。 データは平均値±s.e.m.として示す<2134><6340><466><2134><831><3704><9687>5.2. 唾液腺と涙腺の再生
ドライマウスとドライアイは一般的な症状です。 唾液腺疾患には、唾液腺腫瘍、閉塞性疾患、感染症、シェーグレン症候群、リンパ腫、代謝性疾患などの全身性疾患の症状が含まれる 。 これらの疾患は、涙腺にも影響を及ぼし、ドライアイを引き起こします。 これらの外分泌腺に関連する機能障害や疾患は、一般的に生活の質を低下させる結果となります。 しかし、ドライマウスやドライアイを特徴とする疾患に対する現在の治療法は、その症状を治療するのみです。 私たちのグループは、ED13.5-14.5マウス胚唾液腺胚由来の上皮細胞および間葉系細胞から、私たちが開発した器官胚法(図4b)によってバイオエンジニアリングされた唾液腺胚を再構成し、より良い治療法の開発を目指しました。 唾液腺を摘出した後、生体移植を行うと、生体移植唾液腺胚は成熟した唾液腺に成長し、宿主唾液管と生体移植唾液管は適切に接続されました(図 4b)。 この手順により、レシピエントマウスの唾液腺管は、天然の唾液腺に類似した腺房組織構造を持つ連結型唾液腺となった(図4c)。 バイオエンジニアリングされたSMGは、漿液腺細胞を再生し、自然な器官構造を示していた。 このバイオエンジニアリング唾液腺への神経侵入も認められ、クエン酸を用いた味蕾刺激により唾液分泌が誘導された(図4d)。
また、ED16.5マウス胚の涙腺胚から得られた上皮細胞と間葉系細胞からバイオエンジニアリング涙腺胚を再構築した. 器官原基法を用いて作製したバイオエンジニアリング涙腺原基は、枝分かれした形態形成に成功した。 移植後、これらの腺はin vivoで成熟した分泌腺構造に発達した。 この結果は、器官胚芽移植によるバイオエンジニアリングされた分泌腺の再生の可能性を確認した。
多能性幹細胞からのミニオーガンとしてのオルガノイドの生成
胚発生における器官形成場の誘導過程とその後の自己組織化を再現するコンセプトに基づき、臓器の部分構造と機能を再現するオルガノイドを多能性幹細胞から生成させた。 この誘導は、胚におけるシグナルのパターニングと位置づけを模倣したサイトカインの様々な組み合わせによって実現された。 このコンセプトは、ES細胞から視神経杯オルガノイドの作製に成功したことで初めて証明されました。 その後、頭部では網膜、下垂体、大脳、内耳、毛包、胸部では甲状腺、肺、腹部では小腸、胃、腎臓など、各器官形成領域でさまざまなオルガノイドが誘導された。
腸、肺、胃、膵臓などの成体組織幹細胞も、ニッチの自己組織化によりオルガノイドを生成し、元の組織構造を一部再現することが可能である。 オルガノイドの定義は、その起源(多能性幹細胞や組織幹細胞)によって若干異なりますが、オルガノイドは臓器や組織の構造を部分的に再現し、限られた小さなサイズまで成長できるため、ミニオーガンと考えられています。 したがって、バイオエンジニアリングされた臓器胚とは異なり、オルガノイドは単独では同所移植後に元の臓器の機能を完全に代替することはできないが、複数のオルガノイドを同所および異所移植することにより、臓器機能を部分的に回復することができる。
最近、我々はマウス ES 細胞から生体内で完全に機能する唾液腺の再生に成功した(図 4e,f). 一般的なオルガノイド形成法を用いて、器官形成野(口腔外胚葉)を誘導することで唾液腺原基をオルガノイドとして生成し、これを同所的に移植したのである。 移植されたオルガノイドは、腺房組織などの正しい組織構造を持ち、PG管や神経などの周辺組織と適切な結合を形成した成熟唾液腺に成長しました。 さらに、再生した唾液腺はクエン酸による味覚刺激に反応して唾液を分泌し、オルガノイドの同所移植後に元の唾液腺の機能が完全に回復することが実証されました(図4f)。 これらの研究は、胚性臓器誘導能を持つ幹細胞ではなく、多能性幹細胞に臓器形成場を誘導して作製したオルガノイドを用いた臓器機能再生の実現可能性を明確に示している。 肝臓や腎臓などの大きな臓器のオルガノイドを適切な大きさに成長させることができる新しい体外培養系の開発は、臓器再生の実現に向けた次の研究テーマとなるはずです。 したがって、臓器系全体の再生は、再生医療分野の次の課題である。 IOSは生体内で最も大きな臓器系である。 このシステムには、表皮、真皮、皮下脂肪からなる皮膚組織に加え、毛包、皮脂腺、汗腺などいくつかの器官が含まれています。 皮膚器官系は、水分や皮脂の分泌、紫外線や毛幹による外的刺激からの保護など、恒常性維持に重要な役割を担っています。 重度の火傷による皮膚の損傷は生命を脅かす。 先天性欠損や皮膚付属器の欠損はQOLに大きく影響するが、表皮シートによる部分的な再生医療が可能である。 表皮と真皮からなる人工皮膚の作製や、細胞操作による毛包器官の再生などが報告されている。 しかし、皮膚の器官系は再生されていない。
最近、我々はマウスのiPS細胞から得た胚様体(EB)に器官形成場を誘導し、IOSを再生することに成功した(図5a)。 胚様体を副腎皮質包に移植したところ、腫瘍化することなく、毛包、皮脂腺、皮下脂肪組織などの皮膚付属器の発生がバイオエンジニアリングされたIOSで確認されました(図5b,c)。 さらに、バイオエンジニアリングIOSにおける再生毛の数と密度は、天然毛髪に見られるものと同じであり、IOSにおける器官形成は、通常の発生と同様の方法で行われたことが示唆された。 副腎皮質で生成された生体工学的IOSは、ヌードマウスの背部皮膚に移植した後、毛周期を繰り返すことからわかるように、完全に機能するようになった(図5d)。 この研究により、生体内における臓器系の再生という概念が証明されました。 実用化の観点からは、試験管内で器官系を生成する新しい戦略が望まれている。 そのような戦略の一つとして、複数種類のオルガノイドをパーツとして組み立てることが考えられる。 9388> 図5.オルガノイドの構成を制御して体外で培養する研究は、再生医療分野の次のトレンドになると思われる。 iPS細胞から3次元IOSをバイオエンジニアリングする。 (a)皮膚形成場とその後の器官系誘導シグナルによる多能性幹細胞からのIOS形成のスキーム。 (b) EBs 培養の模式図と、EBs をコラーゲンゲルに空間的に配列して上皮組織を誘導する新規移植法、クラスター化依存型 EB (CDB) 移植の模式図。 スケールバー 50 µm。 (c) iPS細胞由来のバイオエンジニアリングされた三次元IOSの解剖顕微鏡写真(i)とH&E染色(ii)。 スケールバー 500 µm。 (d) バイオエンジニアリングされたIOSの移植前(i)と移植後(ii)の皮膚片の解剖顕微鏡写真。 皮膚片の移植後に毛幹の噴出と成長が起こったことに注意。 スケールバー:200μm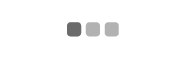
結論と今後の展望
この10年間、生体工学技術から出発した臓器再生研究は、幹細胞生物学や発生生物学の概念を取り込み、臓器再生療法の実現に向けて大きく前進してきた。 オルガノイド研究の成果から、多能性幹細胞や組織幹細胞からほぼ全てのミニオーガンが作製可能であり、臓器再生治療の細胞源に関する懸念が払拭された。 胚性器胚芽から分離した細胞、器官誘導能幹細胞、多能性幹細胞を用いた外胚葉性器官の機能的再生は、臓器置換療法の概念を証明した。
複数の臓器と器官系の機能的再生を実現するには、オルガノイドと器官胚芽を適切なサイズまで増殖できる体外三次元培養システムの開発が不可欠である。 現在のin vitro培養系では、主に栄養供給不足により、これらの組織内部に壊死が出現し、オルガノイドや器官原基を適切に増殖・維持することができない。 生体内では、酸素運搬、栄養供給、老廃物除去など、臓器機能の維持に血液循環系が不可欠である。 最近の組織工学の進歩により、血管網が細胞スフェロイドの内部に生体物質を投与していることが明らかになってきた 。 さらに、血管網を利用した臓器灌流培養システムを開発し、ラット肝臓を長期間健全な状態に維持したことから、新しい三次元培養システム開発の手がかりを得ました。 現在、臓器胚葉法による毛包の再生は、男性型脱毛症の患者さんを対象に前臨床試験を実施し、2020年の臨床試験実施を目指しています。 この毛包再生治療は、臓器再生治療のマイルストーンとなり、臓器再生医療を実現するための材料・対応基盤の整備につながるものと考えています。 毛包再生の知見や臨床試験で得られたノウハウを他の臓器胚やオルガノイドに応用すれば、今後数十年で多能性幹細胞や組織幹細胞からオルガノイド技術と組み合わせて他の臓器を再生することが可能になります。
データアクセス
この論文に追加データはありません
著者の貢献
本総説はT・Tがデザインしました。 E.I.、M.O.、M.T.、T.T.は原稿を書いた。
競合利益
この研究は理研とオーガンテクノロジーズの発明契約に基づき行われた。
資金
本総説は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(A)(課題番号25242041)およびオーガンテクノロジー株式会社からの共同研究助成(T.T)により一部支援されたものである。 本研究は、オーガンテクノロジーズ株式会社から一部資金提供を受けた。
謝辞
原稿中で言及した実験を行った研究室のメンバーに感謝する。
脚注
原著者および出典をクレジットすることを条件に、無制限の使用を認めるクリエイティブ・コモンズ表示ライセンスhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/の条件に基づいて英国学会から出版されたものです